2013年10月12日11:55 AM カテゴリー:
うつ病
うつ症状とは?
うつ病はメンタルヘルス障害の内の一つになります。また、気分障害として総称されています。
近年、確かに多くなっていますが、古代からある病気で、精神疾患の中で最もよく起こる病気です。
うつ病は、20世紀の初めに、躁うつ病として大きく括りこまれ、概念をはっきりとさせられてきました。
その後、アメリカ精神医学会が、DSM-Ⅲという診断基準をだし、2013年に、DSM-Ⅴという最新の診断基準が発表されました。
それによりますと、抑うつ気分や、興味または喜びを感じないことが、うつ病判断のキーワードになるようです。
しかし、観察者(医師)による判断の占める割合が増えたとされており、問題点も指摘されているようです。
なぜうつ病は起こるのか?
一つには遺伝的要素があります。
遺伝が関係する確率は30~50%とされています。これは、生活習慣病を引き起こす可能性のある糖尿病や高血圧の遺伝的関与とほぼ同じになります。
2つ目は、環境です。
ストレスがうつ病の発症に関連しているという報告が、最も多くあります。
ストレスの中でも、生まれてから思春期までの育てられる環境でのストレスが、問題のようです。それにより、脳に変化を引き起こし、成人になってからのストレスで、発症する形が最も多いとされています。
成人後のストレスの代表は、働くこととのようです。少し古いデータですが、平成14年の厚労省の調査によりますと、自分の仕事や職業生活に関して、「強い不安、悩み、ストレスがある」とする方は、全体の60%を占めていたそうです。
どのようにしてうつ病になるのか?
現在のところ、確定した理論はありません。代表的な仮説は3つあります。「モノアミン仮説」、「ストレス仮説」、「神経可塑性仮説」です。それぞれ簡単に見ていきます。
1.モノアミン仮説
脳の中でモノアミンというホルモンが減少して、うつ病になるという説です。
モノアミンは3種類の神経伝達物質です。この神経伝達物質が少なくなることにより、脳おける情報伝達が上手くいかずうつ症状が生じるとしています。
ただ、量が十分な場合でも、うつ病が起こることもあり、決め手に欠けています。
このことから、モノアミンを受ける取る側に問題があるのではという、受容体仮説も提唱 されています。
2.ストレス仮説
ストレスにより、脳の中の海馬の神経に害が生じ、うつ病になるという説です。
慢性的に強いストレスがかかることによりホルモンの分泌作用が狂い、グルココルチコイドというホルモンが大量に分泌されます。
このホルモンが多くなりすぎますと、脳の海馬の働きが弱まります。これにより、更にホルモン分泌が狂い、グルココルチコイドの量が増え、海馬の働きが乱れるという悪循環が起こります。
海馬は、認知機能に関係していますので、海馬の機能が落ちると、認知機能が抑制されうつ病を引き起こすという考えです。
3.神経可塑性説
ストレス仮説を発展させた仮説といえます。
神経は外界からの刺激により、常に機能的、構造的に変化しています。これを神経の可塑性と呼んでいます。繰り返し練習することで、瞬時に動けるようになったり、暗算が早くなったりするのもそうです。
強いストレスが長期間にわたり続くことにより、グルココルチコイドが増えます。これにより脳の海馬における神経の可塑性に重要な役割を果たす「脳由来神経成長因子」というホルモンの量が減ることが分かってきました。
また、このホルモンは神経を新しく作り出すことにも深く関係しています。
脳由来神経成長因子が減ることにより、からだだけでなく、脳の働きも落ちていきます、これによりうつ病が起こるという考えです。
現在のところは、この仮説が有力です。
うつ病と性格、考え方は関係するか?
少し乱暴ですが、簡単にまとめますとうつ病とは、ストレスが長期間に渡りかかり、脳を栄養するホルモンが減ることや、脳においての情報伝達が上手くいかずに起こる病気といえます。
よく言われる、「性格の問題」、「考え方の問題」は、そういう観点から観察しますと、当てはまるかもしれません。しかし、長期に強いストレスがかからなければ、起きないわけですから、大きく関係しているわけではありません。
うつ病になりにくい性格であっても、長くひどいストレスに直面すると、うつ病になる可能性が高いといえます。
誰にでもなる可能性のある病気といえます。
うつ病関連リンク
・
【うつ病】大阪府、30代、男性、鍼灸治療のケース
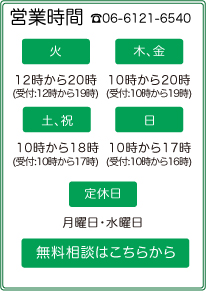
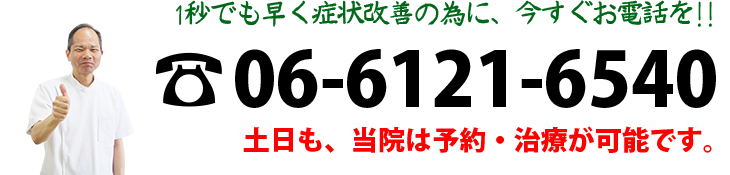 トップページへ戻る
トップページへ戻る
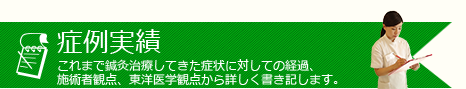
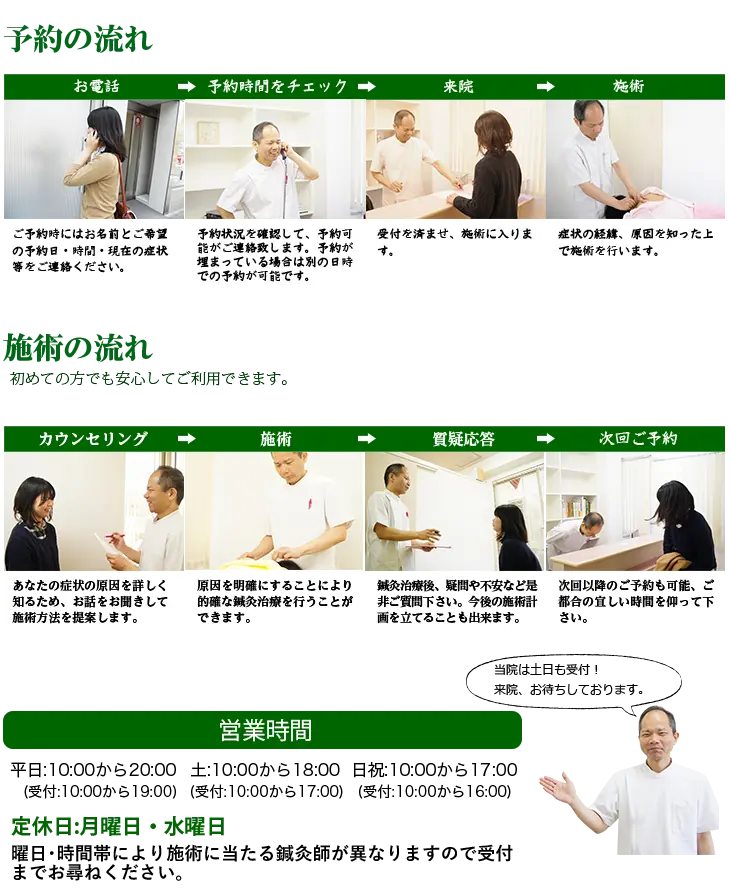
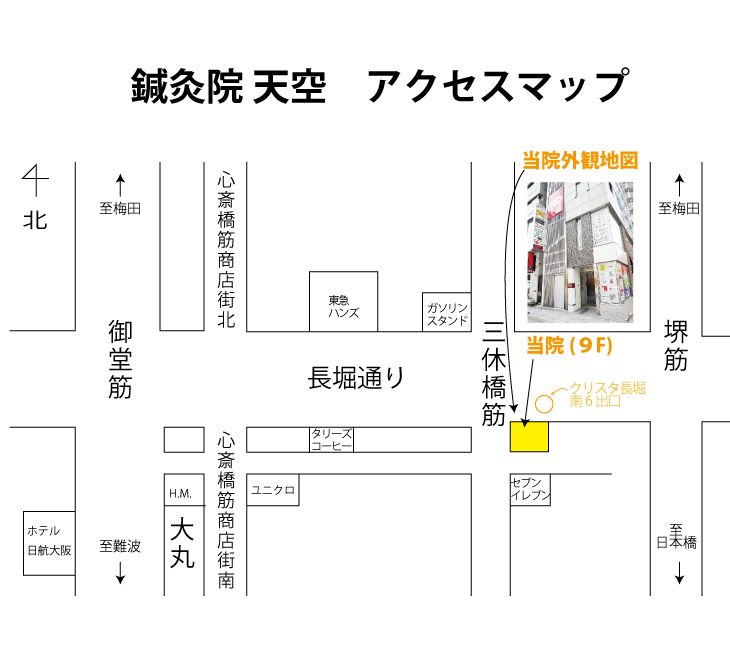
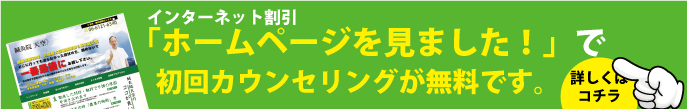

 トップページへ戻る
トップページへ戻る